暑い日が続きます。
太陽光発電事業の観点からは、冷房による電力需要があるため、発電した電力の「行き先」が確保されている、という見方もできるかと思います。
そのような中で、7月9日付で、マイナビニュースに「再エネ余剰電力を冷房に活用。大阪公立大学や三菱重工らが舞洲で実証試験」と題する記事が掲載されています。
記事によりますと、大阪公立大学は、再エネの余剰電力を冷房に活用する新システムを開発。
舞洲の「アミティ舞洲(障がい者スポーツセンター)」に導入し、7月1日より実証試験を開始したとのことです。
このシステムは、再エネの拡大の“足かせ”となっている余剰電力を活用し、 電気エネルギーを冷房に直接使える熱エネルギーとして、大量かつ安価に蓄え、 わずかな電力で汲み出して使えるようにするもの。
基盤技術となっているのは、帯水層蓄熱(ATES:Aquifer Thermal Energy Storage)と呼ばれる方式。
地下水に冷熱を蓄えて再利用する、地中熱活用の仕組みです。
今回の実証試験では、これに「多重蓄熱機能」と「短周期蓄熱・放熱機能」を追加した 新しいシステムを構築したとのこと。
これにより、春や秋など空調需要が少ない時期に発生しやすい余剰電力を吸収し、 冷水(約5℃)として地下に保存。
真夏に冷房として活用することで、発電と需要の“時間差”を吸収する役割を果たすそうです。
蓄電池や水素よりも低コストとされており、大量蓄熱が可能という点も、注目されています。
記事では、「見なし充放電効率(蓄電池と見なした場合の効率)」で評価するとの記述もあり、エネルギー変換の新たなベンチマークとしても位置づけられているようです。
太陽光発電は、発電量が多いときほど使い道に悩む。
その典型が、春・秋の日中の余剰電力でした。
今回のような実証が進むことで、「余剰の出口」が 少しずつ形になっていくのかもしれません。
![]()
太陽光発電ランキング
ブログ更新の励みになります。
よろしければ、是非クリックください。
![]()
にほんブログ村
 <
<

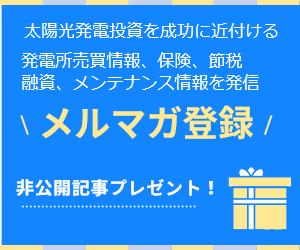


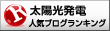
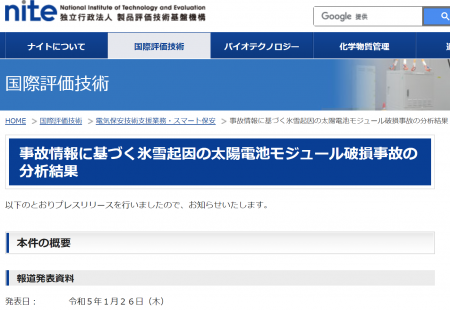
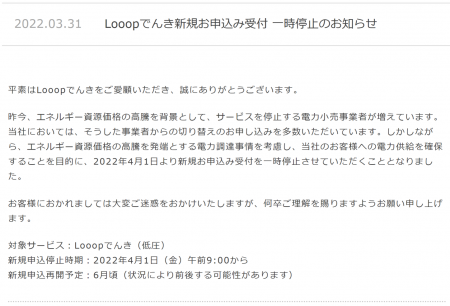



コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。