再エネ賦課金不要論――その背景と真実、そして「FIT期間終了後も稼働を続ける太陽光発電所」の重要性
―「再エネ負担金の持ち逃げ」論に異議を唱える観点から―
1.再エネ賦課金とは何か?制度の必要性とその経緯
まず、再エネ賦課金(正式名称:再生可能エネルギー発電促進賦課金)は、電気を使う全ての利用者が電力量に応じて負担する仕組みです。 えねがえる+3関西電力 法人向けソリューション紹介サイト+3accel. – カーボンニュートラルを加速させるメディア+3
この制度の目的および背景を整理します。
必要性・背景
- 日本は化石燃料を海外から大量に輸入しており、エネルギー自給率が低いという構造的課題があります。 cdedirect.co.jp+1
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス)の導入を進めるため、2012年に 固定価格買取制度(FIT) が導入されました。 三井物産+1
- FIT制度により、事業者は一定期間・一定価格で発電電力を売ることが保証され、その買取費用を補填するために再エネ賦課金が制度設計されたのです。 yonden.co.jp+1
- 実際、太陽光など再エネの割合は、2011年度10.4%から2022年度21.7%へと拡大しています。 JPEA+1
このように、再エネ賦課金は脱炭素・国内再エネ拡大という国策と密接に関係し、国民にも「エネルギーをみんなで支える」という意義があります。
2.再エネ賦課金の“持ち逃げ”論?卒FIT後・安価な電力を還元するという構図
不要論を唱える論者は、「なぜ電力利用者が負担を強いられるのか」「将来還元されるのか疑問だ」「FIT後発電所が撤退すれば回収できないのでは」と指摘します。これに対して本記事では、以下のような論点で反論・整理します。

安価な電力の還元メカニズム
- FIT制度の買い取り価格は通常の市場価格より高めに設定されており、導入拡大時期には賦課金負担が増加しました。 太陽光発電ならソーラーフロンティア+1
- しかし将来的には、FIT期間満了(いわゆる「卒FIT」)を迎えた太陽光発電所が市場電力として低単価で運転継続すれば、 電力利用者にとって安価な電力供給還元が実現可能です。例えば、 卒FIT制度 の議論でも、2032年以降の産業用太陽光FIT満了後も「長期安定稼働」が鍵であると示されています。 経済産業省+2オムロン ソーシアルソリューションズ+2
- つまり、「賦課金を負担して終わり」というわけではなく、「その後、安価な再エネ電力として還元される」ことが制度設計上の肝です。
FIT後の撤退懸念とその対策
- 「FIT満了=撤退」という論調がありますが、実際には多くの発電事業者が FIT満了後も稼働継続する意向を持っており、2032年以降も発電を続けるためのリプレースや運用体制が検討されています。 経済産業省+1
- 例えば、設備の再投資・蓄電池併設・自家消費・PPAモデルなど、FIT後の収益確保策が広がっています。これが「撤退前提の論調こそが国民にとっての悪である」という観点につながります。
3.「不要論」が指摘する課題と、その上で制度を維持・進化させる視点
不要論には確かに説得力のある指摘もあります。主な論点とそれに対する考察を以下に整理します。
🅰︎ 論点:賦課金負担の家計への影響
- 2025年度の賦課金単価は 3.98円/kWh と発表されました。 エネマネX
- 電力量が多い家庭・商業用施設では負担が増えるため、「家計支援として賦課金を削るべき」という声があります。 省エネドットコム
→ ただし、ここで重要なのは「賦課金=単なる負担」ではなく、「将来の電力還元インフラのための投資」であるという視点を失わないことです。
🅱︎ 論点:制度の透明性・公平性
- 再エネ発電設備を持つ事業者・家庭では、賦課金が免除されていたり、自家消費により負担軽減が可能なため、「設備を持てない人との格差」が指摘されています。 太陽光発電ならソーラーフロンティア+1
→ だからこそ、将来の電力還元をしっかり保証し、制度の「恩恵を受けられない人への配慮」が必要です。
🅲︎ 論点:卒FIT後の運用継続・設備廃棄リスク
- 卒FITによる事業撤退・設備廃棄の可能性が、賦課金を負担した国民から不安視されています。 MRI
→ 重要なのは、政府・自治体・事業者が「撤退ではなく継続稼働を前提とした制度設計」を進めているという点です。
4.提案:制度を国民の益に転じるための視点
制度をより納得できるものにするためには、以下のような施策が有効だと考えます。
- 卒FIT環境の明示:2032年以降、産業用太陽光がFIT満了を迎えることを国・事業者が周知し、「稼働継続モデル」を示す。 経済産業省+1
- 蓄電池並びに系統運用強化の制度化:日中発電のみという太陽光の課題を、蓄電池+システム運用で解消し、「安価な電力を24時間提供する」モデルを構築。これが賦課金負担軽減の鍵。
- 負担者と受益者の構図を可視化:賦課金を負担する家庭・事業者に対して、将来的な「電力還元」「設備稼働継続」の見通しを提示することで不安を軽減。
- 設備持たない層への配慮:設備導入できない世帯・中小事業者も恩恵が受けられる仕組み(例:地域PPA・共同所有モデル)を促進。
まとめ
再エネ賦課金は、単なる「負担増」ではなく、将来の安価電力還元・エネルギー自立・脱炭素という大きな仕組みの一部です。
不要論が指摘するように、負担感・制度の公平性・卒FIT後のリスクは無視できませんが、制度放棄・撤退前提では国民の利益は守れません。むしろ「みんなで負担し、みんなで恩恵を享受する」という正しい情報を発信していくことが重要です。
むしろ指摘すべきは、事業者の投資回収と利益回収が終わり、国民への還元をせずに、FIT期間が満了後に即撤退する再エネ設備では無いでしょうか?
土地が賃貸である、危険な立地、設備である等の状況でない限り、事業継続を促すことこそ、国民の利益であり、撤退前提、大量廃棄前提で報道する人々は誰の味方なのでしょうか?

出典一覧
- 四国電力「再エネ賦課金ってなに?」 (yonden.co.jp) yonden.co.jp
- 関西電力「再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)とは?」 (sol.kepco.jp) 関西電力 法人向けソリューション紹介サイト
- U-POWER「再エネ賦課金の全てを解説!仕組み、計算方法」 (u-power.jp) U-POWER
- 経済産業省「次世代型太陽電池戦略」2024年11月28日版(FIT/FIP・2032年以降の継続稼働言及) (meti.go.jp) 経済産業省
- 社会ソリューション「産業用太陽光発電はFIT終了の20年後どうなる?」 (2024年4月22日) オムロン ソーシアルソリューションズ
- エネルギー関連解説「2025年度再エネ賦課金は3.98円!値上がりの要因と推移」 (enemanex.jp) エネマネX

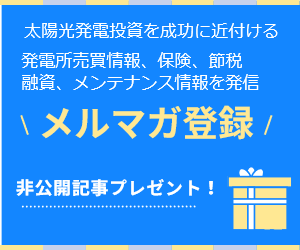




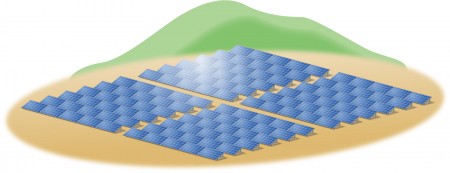







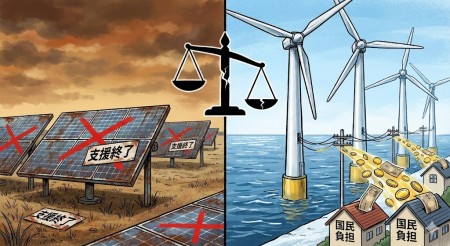


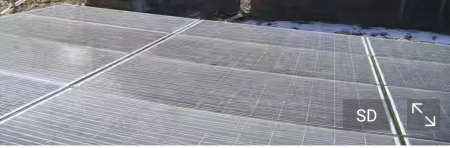

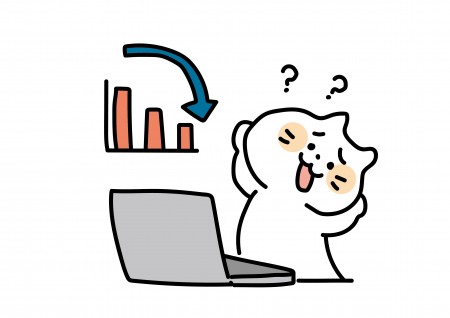



コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。