メガソーラー“転売ビジネス”横行の闇 —— その言説、本当に正しいのかを検証する
近年、メガソーラーを巡る批判的な論調がネットやテレビで目立つようになりました。
特に多いのが、
「悪質な業者が分譲して転売する。売ってしまえば責任ゼロ」
「メガソーラーの多くは転売目的で作られている」
といった刺激的な文言。
確かにこうした言葉は、人の心を強く揺さぶる“叩きたくなる要素満載”のフレーズです。
SNSやニュースサイトが好む「怒りを喚起するキーワード」が並んでおり、転載・拡散されやすく、読者を惹きつける構造にもなっています。
ただし、本当にそれは正しいのでしょうか?
本記事では、メガソーラー批判で使われがちな「分譲=悪」「転売=悪」という構図が持つ矛盾を指摘しつつ、冷静な視点で“メガソーラー転売問題”を読み解きます。

■ 刺激的な言葉ほど拡散される ― メディアとSNSの構造
今回問題になっているような言説が広がりやすい理由はシンプルです。
● 人は「叩きたくなる対象」が好き
「悪質」「責任逃れ」「横行」
これらの言葉は、読者に“怒り”や“正義感”を呼び起こし、シェアされやすくなります。

● 論理の粗さより、キャッチーさが優先される
・詳しい制度
・現実的な運用
・販売スキームの種類
こうした複雑さは省略されがちで、
“悪い業者が転売して逃げている”
という単純構図の方が理解されやすく、クリックも伸びるため重宝されます。
■ 「分譲 → 転売 → 悪」の図式は本当に成立するのか?
批判的な論調では、
分譲して売る → 転売 → 責任放棄
という流れが“悪事の証拠”として語られます。
しかし冷静に考えると、この構図には大きな矛盾があります。
■ 分譲住宅・分譲マンションは?
もし「分譲して売ることが悪」であるならば、
・分譲マンション
・分譲住宅
・土地分譲
・建売住宅
・アパート分譲
・事業用不動産分譲
これらはすべて
「転売目的の悪徳商法」
という話になってしまいます。
当然ですが、そんなことはありません。
● 分譲とはあくまで「商品として販売する」行為
不動産・設備・建物には、
作る人(開発)と買う人(投資者・利用者)
が存在するのは当たり前のことです。
ソーラーも同じであり、
分譲=悪質
という決めつけは、論理的にも成立しません。
■ 「売ったら責任ゼロ」は誤解を生む表現
メガソーラーの分譲スキームには複数の形があります。
- 土地込みで売るケース
- 土地は借地、設備のみ売るケース
- 運用管理は売り手側が継続するケース
- O&M(メンテナンス)を外部委託するケース
つまり、
“売った瞬間に全責任が消える”
わけではありません。
● 法的責任の所在は状況による
- 工事の瑕疵
- 土地の負担
- 造成の問題
- 伐採許可の適法性
- 環境影響評価との整合性
などに関しては、販売後でも責任を問われる場合があります。
「売れば逃げられる」という言い回しは、極めて誤解を生む単純化にすぎません。
■ “転売目的の開発”があるのは事実。しかしそれ自体は悪ではない
不動産開発では、
- 開発したものを売る
- 開発途中で権利を売る
- 竣工後に利益確定のため売却する
こうした行為は一般的です。
メガソーラーの場合も、
- FIT(固定買取制度)終了前の駆け込み案件
- 投資家への販売ビジネス
- 金融商品としての太陽光発電設備
などが存在するだけで、これは合法的な事業モデルです。
■ 問題がある場合は「転売」ではなく“ずさんな開発”
本当に問題となるのは、
- 違法伐採
- 造成不足
- 排水計画の不備
- 保安基準を満たさない工事
- 行政手続きの欠落
といった“開発過程の問題”です。
転売そのものを悪と捉えるのは論点のすり替えであり、
本質は 「適切に設計・造成・許可が行われていたか」 です。
■ あえて言うなら、今回の記事は「突っ込み待ち」に見える
今回フライデーの記事から引用すると
「悪質な業者は土地とソーラー施設を分譲して転売」
「売ってしまえば責任がなくなる」
「多くが転売目的だと私は見ている」
と、あまりにキャッチーな“突っ込み待ちワード”が並んでいます。
正直なところ、
「メガソーラー叩きに乗っかって記事書いたら稼げそう」
という印象すら受けます。
■ まとめ:叩きやすい構図が拡散される――だからこそ冷静に
SNSやメディアは、以下のようなキーワードが好きです。
- 「悪質」
- 「横行」
- 「責任逃れ」
- 「闇」
- 「転売ビジネス」
こうした言葉は拡散しやすく、
「叩きたい心理」を刺激するからです。
しかし、
分譲=悪
転売=悪
という単純な構図で語ると事実を見誤ります。
メガソーラーは複雑な制度・設備・契約の上で成り立つ事業であり、
問題の本質は “ずさんな開発” や “手続きの欠落” であって、
転売そのものではありません。
情報が溢れる時代だからこそ、
私たち自身も 「感情より、事実を見て判断する力」 が求められています。

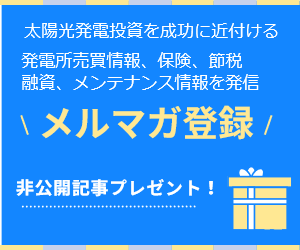

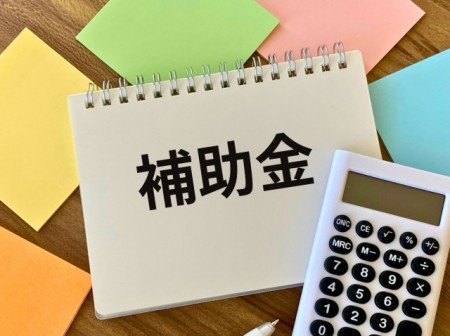


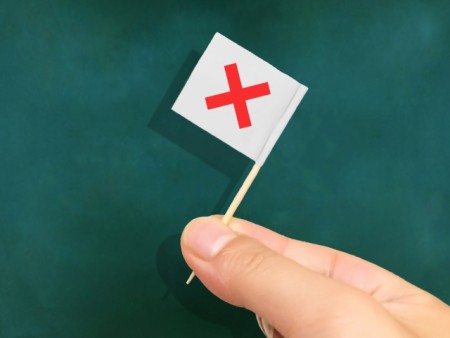




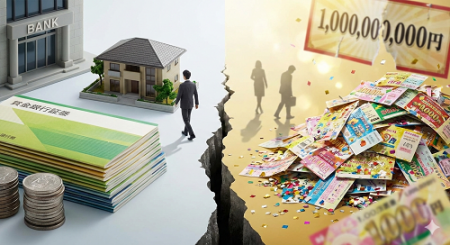





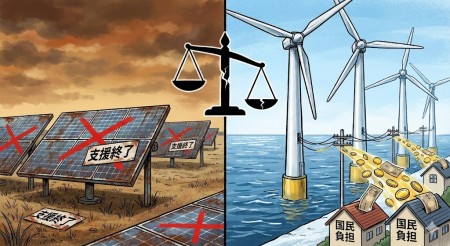


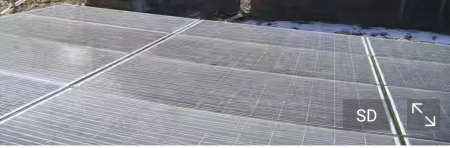

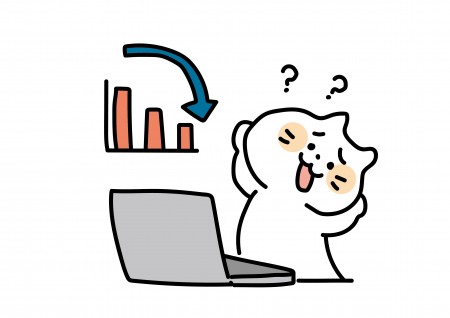

コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。