生成AIを使っていて、「あれ?なんかこの答え、変だぞ」と感じた経験はないでしょうか?
当方も最初は戸惑いました。ぱっと見は正しそうな回答でも、実際には事実と異なる内容が紛れていることがあるのです。
これは「ハルシネーション」と呼ばれる、生成AI特有の現象です。
今回は、ハルシネーションとは何か、なぜ起きるのか、そしてどう対策すればよいのかを、当方自身の整理も兼ねてまとめてみます。
この性質を理解しておくだけで、生成AIをより安全に、そして賢く活用できるようになります。
■ ハルシネーションとは?
ハルシネーション(Hallucination)とは、生成AIが事実とは異なる、もっともらしい“ウソ”を生成することを指します。
たとえば、以下のようなケースです。
-
実在しない論文や人物を引用する
-
ありえないURLや法則を提示する
-
「それっぽい」けれど根拠のない説明をする
生成AIは「言葉を統計的につなげて文章を作る」仕組みなので、必ずしも正しい情報を参照しているわけではありません。
つまり、出力結果が「自然な文章に見える」ことと、「正確である」ことは別問題なのです。

■ ハルシネーションが問題になる場面
日常のちょっとした調べもの程度であれば、多少の誤りも笑って済ませられるかもしれません。
しかし、以下のような場面では深刻な問題につながる可能性があります。
-
医療・法律・金融などの専門分野
-
実在する人物や企業に関する記述
-
引用や出典が求められるレポートや論文
-
ビジネス文書や社外資料への使用
特に、AIの言い回しが自然な分、人間側がウソを見抜きにくくなっている点に注意が必要です。
■ ユーザーができる3つの対策
生成AIの仕組み上、ハルシネーションを完全に防ぐのは現時点では困難です。
ですが、ユーザー側でのちょっとした工夫や意識で、リスクを減らすことは十分に可能です。
1. 出力を鵜呑みにしない(ファクトチェックは必須)
AIの回答をそのまま信用するのではなく、自分で調べて裏を取ることが基本です。
特に「それっぽい用語」や「見慣れない名前」は、検索して検証する習慣をつけましょう。
2. ハルシネーションを起こしにくいプロンプトの工夫
曖昧な問いかけは、AIが勝手に“それっぽく”補完してしまいがちです。
なるべく具体的に、明確な前提を伝えることで、誤った出力のリスクを下げられます。
例:
×「〇〇について教えて」
○「〇〇の定義と、国内での活用事例を3つ教えてください。出典がある場合はURLも添えてください」
3. 用途によってAIを使い分ける
-
アイデア出しやたたき台の作成には非常に有効
-
正確性が求められる場面では、確認・監修が必要
生成AIは、「ゼロから人間が考える手間を減らす道具」として使うのが現実的です。
最終的なチェックや責任は、やはり人間の側が担う必要があります。
■ まとめ:生成AIは賢いが万能ではない
生成AIは、非常に強力なツールです。ですが、それはあくまで「道具」であり、その出力にはクセや限界があるという点を理解して使う必要があります。
今回ご紹介した「ハルシネーション」という性質も、知らずに使うとリスクになりますが、知っていれば安全にコントロールできるものです。
次回以降の記事では、こうした生成AIとの“安全な付き合い方”や、信頼性を高める活用の工夫についても掘り下げていく予定です。
興味のある方は、ぜひ引き続きご覧ください。
![]()
太陽光発電ランキング
ブログ更新の励みになります。
よろしければ、是非クリックください。
![]()
にほんブログ村
 <
<

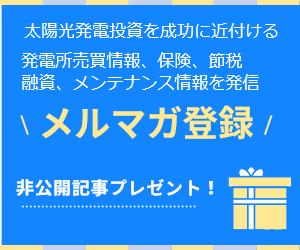

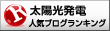



コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。