最近、生成AIについての記事を何本か続けて書いていると、
「これって、全部AIが書いてるの?」と聞かれることがあります。
率直にお答えすると、「基本は自分で書いています」。
ただし、「生成AIの力も、ところどころ借りている」というのが実情です。
今回は、どこまで自分で書いて、どこをAIに任せたのか。
そして実際に使ってみてどう感じたかについて、少し整理してみたいと思います。
AIの知識を整理するために、自分で文章を書く
ここ最近の記事は、生成AIの使い方やプロンプト設計についての自分なりの理解を深める目的で書いています。
文章を書くことで、ぼんやりしていた考えを言語化し、自分の中でも整理することができました。
そのため、記事の構成や言いたいことの順番、伝えたい主旨など、ベースの部分はすべて自分の頭で考えて書いています。
「自分が何をどう伝えたいのか」は、あくまで自分自身の手で組み立てているという感覚です。
AIには、こんな場面で手伝ってもらいました
とはいえ、すべてを一人で完結させたわけではありません。
生成AIには、次のような部分でサポートしてもらっています。
-
文章の読みやすさチェック
文末の重なりや、接続詞のくどさなどをAIに見てもらい、滑らかに整える。 -
具体例の提案
「この場面で例として挙げるなら?」と質問すると、いくつか候補を出してくれる。 -
見出しや装飾の整形
Markdownの整えや、見出しの粒度の統一など。
いわば、「文章の芯」は自分で書いて、「読みやすく整える」「具体例を補う」といった部分をAIにお願いしている形です。
生成AIにおける文章作成の使い方としては、ゼロからすべてを任せるというよりも、自分の考えを出発点にしつつ、整える・補うといった“補助ツール”として活用するのが、今のところ自分には合っていると感じています。
特に、「どこまで任せて、どこから先は自分で整えるか」の線引きは、人によっても、書く内容によっても変わってくるものだと思います。
そのバランスを探りながら、少しずつ使い方をチューニングしている、というのが実情です。
“妙に丁寧”な文体になることも……
ただ、AIが整えた文章には、独特の“丁寧さ”が出てしまうことがあります。
たとえば、「〜することができます」「ご紹介いたします」といった言い回しが続くと、どうしても“AIっぽさ”を感じるのです。
これはプロンプトの設計がまだ甘いという面もあると思います。
「自然な口調で」「少しくだけた文体で」など、指示の出し方を工夫すれば、改善の余地はありそうです。
実際、自分の過去の文章を読み込ませれば、より自分らしい文体で整えてもらえるのかもしれません。
(そこまでは、まだ試していませんが…)
文体には、その人なりの癖やリズムがあります。
そうした“自分らしさ”まで含めてAIに反映させるのは、現時点ではまだ難しいと感じることもあります。
自分の文章とするには、まだ距離がある
正直なところ、AIの出力を読んでいると「うまく書けてはいるけれど、自分の文章とはちょっと違う」と感じることがあります。
言い回しや言葉選び、文のテンポなど、細かい部分に「自分だったらこうは書かないかも」と思う瞬間があるのです。
たとえAIの出力が整っていても、それが「自分の表現」として自然に馴染むには、もう一段階の調整が必要になります。
その意味で、**「そのままでは、自分の文章としては少し距離がある」**というのが今の正直な実感です。
本音を言うと、AIの出力チェックは大変
便利なAIですが、その出力をそのまま使えるかというと、正直、そう簡単ではありません。
-
「この言い回し、ちょっと違うな…」
-
「本当にこういう使い方するだろうか?」
-
「ニュアンスが微妙にズレている」
こういった違和感に気づくには、結局自分の目と感覚で、きちんとチェックする必要があります。
そして、この“確認作業”にどれだけ真面目に取り組むかで、かかる手間は大きく変わってきます。
この作業を丁寧にやればやるほど、「これは自分の言葉として納得できるか?」という基準がはっきりしてくるようにも思います。
(といいながらも、生成AIについての一連のブログでは、生成AIによる文章修正を結構「尊重」しています。
で、やはり「いつもとちょっと文体が違うよなぁ」と思ったり。
ただ、自分の癖として、長文を書くときは雰囲気が変わるので、それもあるかもしれません。)
まとめ:AIは“共作者”として考えている
生成AIは、書く作業を一部効率化してくれますし、発想の補助にもなります。
ただし、最終的な「表現」は、やはり自分の手で整える必要があります。
私自身は、生成AIを“共作者”として付き合っていくつもりです。
現時点では、自分の言葉として“そのまま採用できる”レベルではないことも多いですが、
それでも「使えるツール」であることに間違いはありません。
これからも、より自分らしいアウトプットを目指して、AIの力を“うまく借りる”方法を探っていきたいと思っています。
![]()
太陽光発電ランキング
ブログ更新の励みになります。
よろしければ、是非クリックください。
![]()
にほんブログ村
 <
<

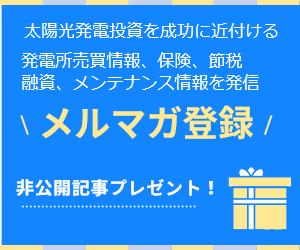

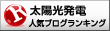



コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。