エネルギー自給率の向上が叫ばれて久しい中で、再エネ設備の方は、果たしてどのような状況でありましょうか。
10月18日付で、高知新聞社が『再エネの発電設備、日本製停滞 海外メーカー高いシェア』と題する、共同通信の配信記事を掲載しています。
記事によりますと、再生可能エネルギーの発電設備における国産化が停滞しており、特に太陽光パネルでは、国産割合が大きく低下しているとされています。
(記事引用)
パネルの出荷に占める国産の割合は2012年に69.9%だったが、22年には11.6%まで落ち込んだ。価格の安い中国製が伸びたのが主因だ。
記事では、経済産業省が再エネ電力と設備の「自給率」をともに高める方針を示しているものの、道のりは遠く、現状では海外製品の圧倒的なシェアが壁となっているとのこと。
また、エネルギー政策が論点となった自民党総裁選では、 高市早苗氏が中国製パネルの市場席巻に危機感を表明し、 国産支援の考えを示したことも紹介されています。
一方で、海外製は円安や輸送コストの影響を受けやすく、三菱商事が秋田・千葉沖の開発計画から撤退した際には、 「海外メーカーの値上げによる影響が大きかった」とのコメントもあったとのこと。
太陽光発電事業を営む者としては、設備の選定において、価格だけでなく、調達の安定性や保守対応の面も、非常に気になるところです。
経産省は、洋上風力設備について、2040年までに国内調達割合を65%以上とする目標を掲げているそうですが、今夏に交わされた欧州企業との協力覚書も、誘致の具体化はこれからとされています。
国産設備の復権は、単なる製造の話ではなく、エネルギーの持続性と、技術基盤の話でもあります。
次世代太陽光発電、ペロブスカイトには大きく期待したいところです。
![]()
太陽光発電ランキング
ブログ更新の励みになります。
よろしければ、是非クリックください。
![]()
にほんブログ村
 <
<

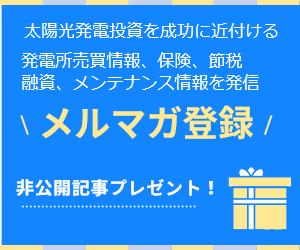

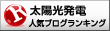





コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。